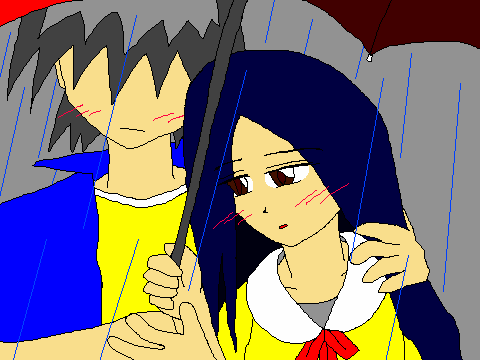
思っていたが、本当に眠くなるとそれもありうるかもしれんな。
今の時刻は午前2時、山藤を寝かせて3時間になるのか。雨の降りは最初からそんなに
変わっていない。まあ雷が鳴らないだけましだけど、今たっている屋上のコンクリート面も
水が溜まっているのが目立つようになってきた。小学生の頃は嬉しげに長靴なんかはいてたけど、
今となりゃ面倒だから用意してなかった。でも靴の中まで水が入り込むと気持ち悪い……
ふと、何か物音か、人の声が聞こえた。誰か屋上から上がってきたのか(学校の警備員に
見つからないように気をつけてるので)少し焦ったが、物音はどうやら天文部の部室から、
山藤が起こしたものだとわかった。いかにも「ドタバタ」という効果音が似合いそうな物音がし、
そして部室の扉が勢いよく開けられる。そこに立っていた山藤は。
「な、なんで起こしてくれなかったのっ!?」
予想してたよりは怒ってはいなかったが、寝起きだからというのもあるが不機嫌そうだった。
あと寝癖が……寝ぼけまなこのまま頭をかいて直してるけど。
「いや……観たいTVなんかあるのならともかく、寝かせてるのに怒ることはないだろ」
「それは……そうだけど、テツが……」
「俺はもう、昼夜逆転して今目が冴えてるから」
半分本当、半分嘘だった。でもまだ起きていられるかな?それは山藤の姿を見たから
目が冴えたというのかもしれないが……
「ほら、そんなところ立ってるとびしょ濡れになるぞ」
雨を気にせず飛び出した山藤は頭から雨をかぶっていて、放っておくと風邪でもひきそう
だった。俺は彼女に近づき、持っていた傘の中に彼女を入れてあげた。わかっていたが……
これは相合傘だ。
「あ……」
それに気づいたのか、山藤もうつむいておとなしくなる。俺は傘の取っ手より上の柄の部分を
持っていたのだが、山藤は両手で取っての部分をつかんだ。二人の手は……まだ離れている。
でももし山藤が相合傘が嫌なら、部室からもう1本の傘を持ってくるだろう。それをしないと
いうことは……俺の方が少し恥ずかしくなってきた。誰も見てないというのもあるだろうけど。
「……フェンスの方、いこ」
「お、おう……」
一緒にいるとはいえ、二人とも無言だった。話すことはない訳ではなかったが、切り出すことも
できずにいた。やっぱり傘の中という今までで一番近い距離にお互いがいるから、
こう意識するのも当然なのだろうけど……てことは今俺は山藤のことを意識してるんだろうな……
山藤の方を横目で見るが、山藤は斜め下を向いて顔は見えない。考えようによっては
目を合わせられないから、とも見えるが……このまま無言で、雨の音だけ聞いているのも
どうなのだろう。今何か話さなければ、ずっとこのままのような気がして……
「……くしゅっ!」
不意に山藤が体を揺らし、小さなくしゃみをした。そういえば雨にぬれてそのままに
してたんだっけ。
「大丈夫か?体が冷えたんなら中に入ってたら……」
話すことは出来た。彼女を思いやる言葉も自然に出た。だが本心は……彼女が中に入れば、
俺はまた一人でここにいなければならない。彼女をここから離したくないのかもしれない。
「ん……平気、ちょっと髪の毛からおちた雫が鼻にさわっただけ」
風邪を引いたわけではないとわかって、かつ一緒にいられて俺は少し安堵した。
少し自分勝手な考えだったけどな……
「髪長すぎるかな、もう少し切った方がいいかな……」
それは独り言にも、俺に尋ねたようにも聞こえた。ここで何か言わなければまた沈黙が
続いてしまう……だが、そう考えるより早く、俺の口と手は動いていた。
「もったいないよ、そんだけ伸ばしてるのに。俺はその髪型のままがいいと思うけど」
俺の手は山藤の髪を頭から、雫を払うようにゆっくりとなでていた。彼女は少しびっくり
したような表情になったが、なすがままにされながら
「そ、そう……かな」
はっきりいって自分でも何をやってるんだと言いたくなった。だが今更やめることもできず、
しばらくなでていたのだが、意を決して手を肩のあたりで止める。そしてゆっくりと彼女の
肩を抱き寄せてみた。山藤は……体を俺に預けてくれた。
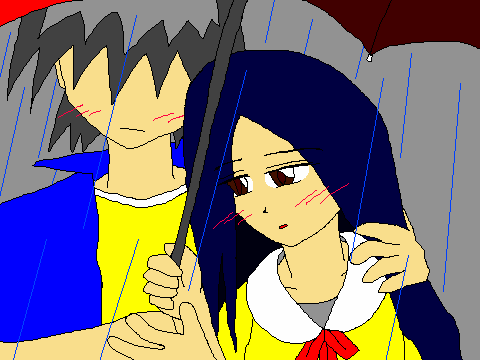
そしてまた無言になった。だが今度は雨の音だけでなく、彼女の息遣いも俺に伝わってくる。
心臓の鼓動もそうかもしれないが、俺自身のものかもしれない。バンドクラブにいたときは
全然感じもしなかったことが、今津波のように押し寄せてくる。生まれて初めて、本当に
人を好きになるということがわかったような気がした……
そのときは、もう隕石のことなどすっかり頭から消えていた。なぜ俺たちがこんなところに
いるのかも考えてもなかった。だから空が一瞬光ったのは、雷でも光ったのだろうと
気にも留めてなかったのだが。光の筋が地面に落ちた衝撃で我に返った。
ドォオオオォン!!
「お、落ちた?!」
先に声をあげたのは山藤だった。しかも落ちたのは、学校の敷地内かそのすぐ外側といった
ごく近い場所。白衣たちよりも先に俺たちが隕石を見つけるのはほぼ間違いない。
これで最悪の事態が起こらなくて済む、山藤も危険な目にあわせなくて……
「……行こう!」
「待って、カメラカメラ」
っとそうだった、俺は一旦部室に戻り、ビデオカメラを濡れないようにビニール袋に
かぶせつつ、また1つの傘で走るのも無理なのでもう1本の傘をつかんで、再び部室を出る。
「改めて……いくぞ!」
「うん!」
2人は隕石が落ちた地点へ駆け出した。これで事件が終わるということを願いながら……